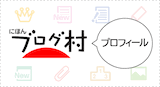はじめに(最悪の事態とは何か)
新型コロナウィルスに関して、最悪の事態、最大のリスクとは何か。
感染して苦しい
医療崩壊が起こる
経済が停滞して不況になる
好きなものを食べることができない
好きなところに行けない
会いたい人に会えない
会社が倒産する
仕事を失う
ボーナスが出ない
給料が減る
受験生であれば試験が延期される
残念ながら全部違います。
コロナに関しての最悪の事態、最大のリスクは、
「あなたが亡くなってしまうこと」
です。
最悪の事態は、「自分自身が亡くなること」です。あなたにとってこれ以上最悪なことはありません。
次に、家族、身近な大事な人が亡くなること、などでしょう。
そのつもりで対策をすれば、第三者に対しても効果があるでしょう。
他のことももちろんリスクとしては大きいですが、最悪の事態は、自分自身が死ぬこと以外には考えれらません。逆にそれ以外は、最悪の事態ではないということです。
最悪を想定できれば、最悪を避けることができます。
「あなたは死んではいけない」「生き続けなくてはいけない」
一番大事なことです。それ以外は、大変には違いはないですが、最悪ではないです。
感染しないとしても大変な状況は容易に予測できます。
そんな状況でもどうか自ら命を絶つことだけはしないでください。
最悪を避けつつできる限りのことをしていきましょう。
予防と対策
厚生労働省のページで確認する
医学的なことは専門的にわかりせんので、法律家の立場から考えます。データ、ファクト、ロジックで考えていきます。
そうするとまずは厚労省の情報から見ていきます。
「新型コロナウイルス感染症について」(厚生労働省HP)
「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」(厚生労働省HP)
医学的な予防や対策は、基本的には厚労省がまとめているサイトを見るのが良いでしょう。裏付けのない情報などが混ざっていることがほぼないため、信頼できます。
あとは感染症対策の医師のSNSとかでも良いのですが、基本的には厚労省の情報を最優先に信頼します。
日々更新されていますので、マメにチェックするのが良いでしょう。
具体的に注意すること

厚労省のページによると、
感染は、飛沫感染と接触感染があり、空気感染は、起きていないと考えられる、空気感染はしませんが、閉鎖空間や密室は避けましょう。
とあります。
厚労省のページを読み解くと、飛沫(くしゃみ、咳、つば など)に最大限注意すべきことが分かります。
確かに、人が多い満員電車では感染の拡大は見て取れません。一方で、お酒を飲んで酔っぱらって、口から泡を飛ばして話しながらご飯を食べたり、口を拭ったりするお酒の飲める飲食店、唾とばしながら熱唱、応援するカラオケ、ライブ、イベント、スナックなどは、感染可能性の高い場所だと判断できますし、感染が多い場所です。
さらに、お触りなどがある夜のお店、接待を伴う夜のお店で感染するのはいうまでもないでしょう。

東洋経済が出している統計が面白くて、基本的には年齢の人口分布に比例して感染者が分布しているのですが、比例していないのが、30~40歳の男性と20歳代の女性です。
人口比率を超えて感染者の割合が多かったです。正確な理由は分かりませんが、それぞれがお互いに濃厚接触をしている環境があるのではないかと推察されます。
データは東洋経済のページが細かく出してくれています。一般的なテレビなどのマスメディア、ネットの情報などよりは、無駄に不安を煽る意図がなく好感が持てます。
改めてデータを見ると、高齢者は重症、死亡のリスクは高いです。一方で40代以下は重症、死亡のリスクはかなり低くなっています。
65歳以上の方、65歳以上の方と同居したり接する機会があったりする方は注意を細心の注意が必要です。
話を戻すと、飛沫に徹底的に注意することが大事です。
空気感染の手前のエアロゾル感染もあるなどの情報のありますが、飛沫感染、接触感染の対策を徹底していれば、対応できるかと思います。不特定多数の人との接触を避け、行動することが重要です。
院内感染が多いのは、物に付いたウィルスを触ることによる接触感染の可能性が高そうです。
高齢者が多く、待合室、エレベーターのボタン、カウンターなど、多くの人が触る場所が多いので、その点は心配です。
あとは、移動の為のバスです。電車に比べて何かに捕まったり、椅子に座るでもどこかに触ることが避けられないと考えます。電車にはないリスクです。
できる限り手袋と手の消毒はした方がいいでしょう。
以下、働きに行ったり生活したりする中で、毎日注意すべきことを列挙します
- 手を石鹸で洗う
- マスクをする(相手のためにも)
- 毎日2回は検温する
- 顔を触らない(マスク、メガネをすれば回避できる)
- 1時間に2~3回換気をする
- 外では手袋を履く
- 他の人が触るであろうあらゆる場所を素手で触らない
- 携帯電話、職場の電話などを消毒する
- ドアノブやトイレなどの消毒
- しゃべっている人がいる場所にいかない
- 公衆トイレは極力使わない
- 買い物の際も手袋をするか、買い物かご、商品などを触った後は直ぐに消毒する
家にいてもすべきことも当然含まれています。徹底しましょう。
感染による3つのリスク
65歳以上の高齢者、疾患がある方は、人との接触は本当に注意しましょう。
感染した場合のリスクとしては、死亡してしまう可能性のほかにもリスクは色々とあります。
以下で、感染した場合に起こり得るリスクをあげていきます。
繰り返しになりますが、あなたにとって最悪の事態は、自分自身が亡くなることです。そして、身近な人が亡くなることです。亡くなることを避け、回復した場合は、苦しさの引き換えに抗体ができます。
全体の割合では、半数は無症状、3割軽症、重症者は2割です。仮にかかっても大丈夫なように、日常的に免疫力を上げておきましょう。
それでは、身体的な問題以外の感染リスクをあげていきます。
2週間業務の停止
基本的には、2週間は自宅待機か入院かです。当然通常の業務はできません。
同じフロアであれば、事務所、会社全体ストップしてしまいます。
一応、フロアが違い、接触していない、対策を徹底している場合には部分的な稼働はできますが、いずれにしても影響は大きいでしょう。
全ての対面業務がストップしてしまうと決済などができなくなります。
少なくとも、資格者の接触を分散して勤務する(一人は在宅、別フロアなど)のリスク管理が必要でしょう。
濃厚接触者も自宅待機などが必要
任意ではありますが、濃厚接触者を洗い出されます。一緒に働いている人、家族は当然です。
2週間以内にお客様に会っていたら感染の旨を連絡するのが筋でしょう。
周りには当然、迷惑がかかるし、信用も失います。
人がたくさんいるような大きな会社と関わりがあった場合は余計に大変です。多くの人に影響が出ます。
個人情報は出ないようにすべきですが、影響が大きいと個人情報がでる可能性もあります。
情報がいったん出てしまうと歯止めが利かずに拡散する可能性があります。
また、夜のお店などに行っているとそれも洗い出されてしまます。
消毒が必要になる
感染者がいたフロアなどは、消毒が必要になります。行動の範囲が広いと大変ですし、大きな迷惑や負担をかけることになります。
司法書士事務所としては、大きく信頼を失うでしょう。
受験生は、精神的にストレスが大きいと思います。
大事なのは、自分が感染しないこと、人に感染させないことです。
事務所で感染者が出ると、業務が止まるのと、お客様に迷惑がかかります。感染者が内部から出ると、事務所がつぶれるくらいの気持ちで細心の対策などが必要です。
感染後の対応
そもそも何をもって感染したと判断するかは難しいです。
検査薬で陽性反応が出たらなのか、症状が出たらなのか。
厚労省のページにある通り、
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
は感染を疑う必要があります。
上記の症状が、自分自身、家族、職場の仲間、職場の人の家族、接触したお客様などに発生した場合は、速やかに情報を共有しましょう。
上記に該当する場合は、病院、保健所に連絡をし、感染と判断されれば、
建物などを消毒する必要があるでしょう。
場合によっては、危急時遺言のご案内などをする必要があるかもしれません。
死亡リスクがある方に提案するのは、精神的な負荷が大きいです。ただ、資格者としてどう行動すべきか、できる選択肢を提案することも必要なのだと思います。
縁起の良い話ではありませんので神経を使うでしょう。
それとなくその話題を出し、不謹慎な空気であったり、それどころではなかったり、そんなときは、話はすぐに引っ込めればいいでしょう。
まとめ

- 最悪の事態は、自分が死ぬこと
- あなたは絶対に死んではいけない、生き続けよう
- 自分と自分の接する大事な人が感染しないよう細心の注意を払う
- 感染したら事務所や仲間は大きな打撃を受けることをメンバー、家族と共有する
- 感染してしまったらすぐにできる限りの対応をとる
医療に従事している方、飲食店やスーパーなどの店舗型のサービス業の方、運送、配送の方はもちろん、それぞれの環境で必死な方、苦しんでいる方、大変な方、
それぞれの方にエール送り、感謝しつつ、
どうかあなたが無事でありますように。
最新記事はこちら