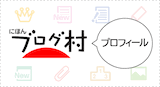リモートワーク(テレワーク)導入を検討している方へ
リモートワークへの取り組みについて色々と聞いてみたけど、実際には取り組んでいる司法書士事務所は少なかった。
でも、実際に取り組んでいる事務所もあって、業績を上げている事務所はほぼ取り入れていました。
急に言われても今まで通りしかできないとか、士業は特別な仕事だからできないんだ、守秘義務があるからとか、色々という方もいるのだけど、そもそもやろうとしていないというのが一番な気がしました。
そんな人たちは置いといて、実際にやろうとしてもできない、という方のために少しでもお役に立てればと考えてまとめてみました。
結論からいうと、完全なリモートワークには移行できていません。
郵便、権利証などの重要書類の預かり、職務上請求などが課題になっています。
逆にそれ以外は意外に行けるかもと思っています。
特に商業登記はほぼ行けるな、と手ごたえを感じています。
部分的にできることをやっていこうと取り組んでいます。
という程度なので、期待に応えられているかは分かりませんが、少しでもお役に立てればと思い綴ります。
改善の余地は十分にあるので、少しずつ改善していきます。
なお、このページは2020年5月時点の情報と見解です。
随時更新はする予定ですが、その点ご了承ください。
働き方改革と緊急事態宣言
やると決める
4月緊急事態宣言が出され、外出自粛や出勤割合を減らす等の要請が出ました。
それを受け、リモートワーク(テレワーク・在宅ワーク)を直ぐに取り入れました。
司法書士の同業や先輩の中には、重要な個人情報を扱っていたり、業務ソフトを扱っているので無理という方もいます。
しかし、事務作業をする場合は、どの業種でも個人情報は扱いますし、できない言い訳をしても何も改善しません。
経営者は、やると決めることが重要だと思います。
やると決めて、「どうやるか」「どこまでやるか」を考えるのが大事です。
そもそも、(緊急時や休日など)家でも仕事ができるように、役員には家のパソコン、モニター、プリンターを購入していたため、役員は既に取り組んでいました。
2020年4月、弊所はリモートワークに取り組むことを決めました。
最初は、一人事務所で、自宅開業の多いでしょう。
在宅ワークなど最初からやっていたのです。パソコン一台でできる仕事なので、部分的にでもできない理由はありません。
そもそも経営者は、既に家でもどこでも仕事しています。
お客様のところに訪問する際にも、ノートパソコンやタブレットで、共有のフォルダにアクセスして情報を確認していていました。
それを他のメンバーにもできる範囲でやってもらうというだけのことです。
今後どうせ必要に
柔軟な働き方は今後の採用に影響するでしょう。
リモートワークを導入することで、子育て世代でも働く選択肢が増えます。
また、提携先や依頼者等も遠隔でのオンライン面談、相談も需要は伸びるでしょう。
そして、既に増えていますが、ビジネスパートナーもリモートでの打合せが増えてきています。
税理士さん、弁護士さん、保険屋さんなどはもちろん、お客様でもオンライン面談を希望する方が増えています。
リモートワークは不可逆的に進んでいくでしょう。
この機会に導入すべきと認識して、取り組んでいます。
東京オリンピックも(おそらく)ありますし、東京都はそもそもテレワーク導入を推し進めていました。
イベントがあると電車通勤は非常に苦痛になるので、その意味からも柔軟に対応できる準備はしておいた方が良いでしょう。
今は補助金もありますし、社会のニーズ、流れもあるので、導入するのはいいタイミングだと思います。
今やるしかない。ということで、導入しています。
リモートワークのために準備すること
機器やソフトなど
ノートパソコン
これは士業事務所としては、必須でしょう。
全員分、ノートパソコンを準備します。
私は事務所と自宅にデスクトップパソコン、別途ノートパソコンを備えております。
リモートツール

そもそも業務ソフトを使わない業務は、ファイル共有ツールなどがあれば十分です。
一方で、業務ソフトなどを使用している場合は、パソコンの遠隔操作できるツールがあると便利です。
パソコンをリモートで操作できるツールがあると、業務ソフトが入っているパソコンを別の(自宅などの)パソコンから操作することができます。
遠隔操作ができると、全部のパソコンに業務ソフトを入れるなどの準備をしなくて済むようになります。
パソコンのリモート操作ツールはいくつか種類があります。
最初は無料でお試しできるものがほとんどなので、試してみることをおススメします。
個人的にはTeamViewerが使いやすいです。
以下で比較していきます。
【パソコンのリモート操作のツール】
| チーム ビューア | マジック コネクト | Gリモート ~ | エニー デスク | |
| 特 徴 | 利用者多い 使いやすい | 高セキュリティ | 個人向け | 設定等簡易 |
| 費用例 | 2,067円~/月 | 18,000円/年 | 無料 | 個人は無料 1,200円~/月 |
| 無料体験 | あり | なし | あり | あり |
| メリット | 利用者多い 操作性良 | セキュリティ高 画面覗き見防止 | 無料で簡単 | アクセスユーザー の記録可 |
| 注意点 | 費用負担大 | フリーズ対応難 個人向け |
【チームビューア(TeamViewer)】
「あらゆるデスクトップやモバイルデバイスからiOSデバイスへの画面アクセスができます。」
と説明にありますが、簡単にいうと、
家のパソコンやスマホ、タブレットから、事務所のパソコンの画面に入って操作することができる。
ということです。
事務所規模ごとにプランが選べます。
利用者が非常に多いので、サービスの改善、向上が常に行われていますので、その点でも安心です。
こういう選択をする場合には、トップシェアか2番手を選択すると、サービス面、コスト面ともに間違いないと思います。
TeamViewerのダウンロードはこちら
【マジックコネクト(MagicConnect)】
すいません、こちらは有料版のみなので、使用していません。
表に出ている情報と使っている人の情報をもとにしたコメントになります。
セキュリティ面は安心ができます。
ただ、USB型、端末認証型はどちらも利点があるようです。
用途に合わせて選択するのが良いでしょう。
どのツールもそうですが、別途WOL(Wake on Lanの略、遠隔でのPC起動ツール)を備えると便利です。
無料のお試しがないので、まずは他のものを試してみて、使い勝手が悪い等の場合に選択すると良いでしょう。
【Googleリモートデスクトップ】
無料で始められます。特殊なソフトは不要ですので、気軽にお試しすることができます。
MacからWindowsパソコンに入って操作することは可能です。
個人で使うには問題ないですが、複数の人が同じパソコン(業務ソフト入りパソコンなど)で使うのは不向きかと思います。
一時的に使うのであれば非常に使いやすいです。
一方で、長期的な使用は不向きな可能性があります。
参照リンク
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4028379/windows-10-how-to-use-remote-desktop
遠隔の電源ツール等(スイッチボット、WOL)
パソコンを遠隔で操作する準備はできても、そもそもパソコンの電源を入れておかないと操作できないものがほとんどです。
そこで、遠隔でパソコンの電源を入れることができるツールをご紹介していきます。
たくさん種類があるので、代表的なものを紹介しますので、お好みのものを探してみてください。
1つ目はスイッチロボット、2つ目はWake on Lanです。
【スマートプラグ、スイッチボット】
遠隔で電源を入れることができるツールです。
正直これは、パソコン以外に使っても非常に便利です。
夏や冬のエアコンなどにも是非とも活用したいツールです。
パソコンに設置して、遠隔で電源を入れて、遠隔操作のツールと合わせて使うことにより、すべて事務所で完結できるようになります。
事務所によっては、業務ソフトが入っているメインパソコンの電源をずっと点けたままにしているところもあるそうです。
リモートができるという点ではそれでも問題ありません。
あとは、セキュリティをどう考えるかです。
外出先や出張中、旅行中に急な連絡でも対応することができるので、在宅に限らず今後の働き方の幅を広げる意味でも活用した方が良いでしょう。
売れ筋のものをご紹介します。
割と簡単なものは、こちらです。ハブがいらないのは便利です。
最初にアプリをダウンロードしてちょっとセットする必要はありますが、あとで紹介するWOLに比べるとこちらの方が断トツで楽です。
安価なので、お勧めです。
こちらは、物理的にボタンを押すものにも対応できます。
デスクトップパソコンのスイッチに設置すると良いでしょう。
個人的にはハブは必要ないと思います。
【Wake on Lan】
遠隔でPCを起動する技術です。
事務所のPC電源がオフだとリモートツールを使用しての遠隔操作はできません。
Wake on LAN を使えば、オフになっているコンピュータの電源を遠隔からオンにできます。
こちらも様々な種類が出ていますので、組み合わせて使うと良いでしょう。
スマートプラグに比べて、設定は大変です。
自分で設定することを諦めました。
こういう設定などが苦にならない事務所メンバーにお願いして設定してもらいました。
「書いてある手順通りに進めれば問題なくできる」と言っていましたが、挫折しました。
慣れないことは、言葉自体が難しし、ピンときません。
専門家として、非専門家に説明する際には気を付けようと思いました。
テレビ電話(オンライン面談)ツール
ズームが非常に流行っていますが、他にも様々なツールがあります。
アカウントを知っていたり、繋がりがあったりする場合は、
ちょっとしたことならLINEのビデオ通話(複数可)、繋がりがあれば、Messengerも使いやすいです。
Messengerは画面共有もできるので、私は税理士さんなどの他の士業などと活用しています。
その他、ビジネスで使えるオンライン電話を比較して整理します。
【オンライン電話サービス】
| Zoom | meet in | ベルフェイス | LINE WORKS | |
| メリット | 知名度高い | 相手が楽 | 相手が楽 録画できる | 簡単 |
| デメリット | 要アプリ | 高コスト | 高コスト | 登録者同士 のみ |
| 受け手の 負担 | 要アプリ 要アカウント | 簡単な入力のみ | 簡単な入力のみ | LINEWORKS 同士のみ |
| 画面共有 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 費用例 | 無料 または 2,000円/月 | 3万円~/月 | 10万円~/月 | 無料~ |
| 無料版 | あり | なし | 期間限定 | あり |
| HP | こちら | こちら | こちら | こちら |
その他、Wherhby(旧アピアイン)があります。PCはそのまま使えますが、スマホはアプリのダウンロードが必要です。
画面共有もできますし、無料版もあります。
有料版は約10$です。
使いやすさ重視、依頼者との面談重視
相手方のアプリダウンロードがないのは、ミートインとベルフェイスです。
それぞれサイトから、ミーティング番号等を入力すれば、直ぐにオンライン面談が始められます。
相手方にアプリのダウンロード等は不要で、直ぐに始められ、非常に便利です。
Webからの問合せに対して、迅速かつスムーズに面談まで誘導することができます。
特に高齢者が多い相続部門をやっている事務所は重宝します。
ただし、いずれも費用はかさみます。ベルフェイスは、月額だけではなく、初期費用も相当程度かかります。
コスパ重視、経営者、ビジネスパートナー、勉強会などとの利用
依頼者との面談ではなく、スタッフやビジネスパートナーである士業等とやり取りする場合、セミナーを開催などする場合は、zoomが使いやすいです。
アプリを入れて頂く必要はありますが、受け手は無料版でも十分なのと、ビジネス版でも安価に導入できることが挙げられます。
ユーザーが多く、知名度も高いので、そこも利点です。
セキュリティが心配な方も多いと思いますが、利用者が多いので、その点は随時改善、更新されるはずです。
ホストがパスワードを掛けたり、参加の承認操作を丁寧にすれば対策できるかと思います。
ある程度ツールなどに慣れている方、何度もやり取りする方は、zoomが便利です。
Teamsは、ビデオ電話としても機能します(し便利です)が、チャットツールとしても有効なので、チャットツールのところで紹介します。
人、情報の管理
顔を合わせていないため、人の管理は重要です。
また、事務所の外で作業するため、情報の管理も対策が必要です。
契約書の締結
この機会に改めて、守秘義務の徹底と誓約書を作成し、メンバーには提出してもらいましょう。
会社PCのみ使用してもらい、個人デバイスは使用不可としましょう。
チャットツールなど
顔を合わせない分、LINE、チャットワーク、スラック、Teamsなどのチャットツールを活用しています。
何かしらの情報共有ツール、連絡ツールは必須でしょう。
弊所は開業時からチャットワークを業務連絡、案件・タスク管理などするために活用しています。
全体会議や個別打合せはzoomを活用しています。
ただ、業務を監視するためにzoomをずっと繋ぐなどはしていません。
そんな監視をされたら1日で辞めると思いますので。
MicrosoftのTeamsも便利です。チャットとビデオ会議も一括でできます。
無料版もありますので、まずは試してみると良いでしょう。
何かしらでチャットグループを作り、業務相談を進めていくと非常に便利です。
内部の管理だけではなく、依頼者と税理士さんや紹介者などを同じグループで案件を進めていくと、報告の漏れもないですので、仲間にも安心感は出ると思います。
ただ、ツールが増え過ぎると管理が大変なので、メインのものを決めておくのが良いでしょう。
ファイル共有ソフト
事務所内での業務中はもちろんですが、自宅作業などの場合は、どこまでセキュリティをかけるかが問題となります。
リモートワークの場合は、事務所内業務よりもアクセスできる情報を限定的にし、現時点の作業に必要な情報のみに限定する必要があります。
必要に応じて、編集不可、印刷不可、閲覧のみとするなどの対応も必要です。
ファイル共有ソフトとしては、boxとドロップボックスがあります。
どちらも利点がありますし、どちらも使っています。
基本的には内部やビジネスパートナーとのファイルはドロップボックスで管理してます。
メインはドロップボックスです。
お客様など外部の方とのファイル共有はboxを使っています。
ただし、明確な線引きはありません。
ドロップボックスは、たまたま開業当初から使っているため、そのまま継続してメインで使用しています。
ドロップボックスは無料プランがありますし、boxも期間限定ですが、無料お試し期間があります。
気に入った方を活用してみてください。
スマホにアプリを入れるとスマホからでもファイルが確認できます。
また、板書やメモなどの写真を撮ると、スキャン機能があるので、ゆがみを取ってくれて、綺麗なPDFにしてくれます。
⇩3年契約ですが、割引の契約をしたい方はこちらから

作業割当、業務整理
おそらくこれが一番大変です。
何を家でやるのか。基本的には書類作成がメインです。
資格者は、書類作成、メール返信、提案書作成、セミナー準備、執筆など、指示を受けなくてもできると思います。
補助者に自宅で何をしてもらうかについては、非常に悩ましい問題です。
後にも挙げますが、そもそもの事務所の業務分担と整理を根本的にしていく必要が出ています。
書類作成(登記書類、議事録、協議書、相続関係図など)と書類内容確認に加えて、販促物作成などを徐々に移行していく予定です。
「決済の書類の授受などと相続の職務上請求による戸籍集中等以外は割といける」
というのが率直な感想です。
逆に上記の2つは諦めて開き直っています。
決済については、銀行に集まらずに、事前に本人確認、書類の受領などをしておき、当日はネットバンクの決済で着金を確認して実行。
というやり方も出始めています。
そもそもネットバンクを使った事務所決済も増えていますので、ほぼ同じやり方です。
業者決済などの場合は、特に進んでいます。そういう点では、働き方は色々な部分で変わっていくのだと思います。
その他
自宅でやる場合は、Wi-Fi設備や電気代などを考慮して、手当を検討する必要があります。
交通費が減る分、在宅手当として支給することはお互いにとってメリットがあるでしょう。
課題

正直課題は沢山あります。全部のリモート導入は到底出来ていません。
特にネックになる部分を挙げていきます。
紙書類問題
権利証、印鑑証明書など、決済に必要な書類の受領や保管は、リモートワークには不向きです。
幸いそこまで決済をする事務所ではありませんが、この点は課題です。
というか、割り切っています。
また、戸籍、職務上請求も、事務所外には持ち出せず、リモート化できません。
付随して、郵便物の受取りも必要なため、最低1人は事務所にいて、郵便物の受取りとスキャン対応をしています。
結局、このような取組みのネックは、行政(書類)と金融機関です。
彼らは既存のルールを守ることの優先順位が非常に高いので、柔軟な対応は時間がかかります。
まだまだ紙文化、印鑑文化が残っています。
不動産登記については、業務整理をし、できる部分とできない部分を分けてやっていくしかないと思います。
相続についても、書類収集、銀行の手続きは事務所での手続きが必要になることが多いです。
重要書類や郵送物を自宅には持ち帰らないようにはしてます。
生前対策(遺言書や家族信託)などの提案書や文案の作成はどこでもできますのでリモート対応可能でしょう。
一方で、商業登記は、印鑑証明書が必要な場合もありますが、基本的にはリモートワークに向いていると感じています。
先方もツールなどに明るい方が多いですので、zoom、チャットワーク、ドロップボックスなどが活用できれば、押印書類、印鑑証明書の送受以外は、全てリモートで完結します。
半分以上は、書類もデータで送り、印刷して送ってくれるので、業務効率は一気に上がりました。
大事なのは、業務を分解して整理することです。
人の問題
業務管理をどうするのか、業務指示をどうするのかは、解決できていない課題です。
資格者は良いとしても、補助者には都度指示を出している状況です。
今後は教育とマニュアル化を進める必要があります。
この点は課題が浮き彫りになっています。
リモートワーク導入のメリット
- 業務の整理ができる
- 移動時間が減る
- 作業効率が上がる(中断されにくい)
- 成果主義になる
- 柔軟な働き方が可能、採用の幅が広がる など
リモートワークを導入するにあたって、業務の見直しをすることができます。
何が必要で何が不要なのか、事務所にいなくてはできないのか、そもそも必要なかったのか、などです。
業務仕分けのいいチャンスです。
業務を中断されにくく、集中しやすくなります。
ただ、家庭に複数人が在宅で働いている、お子さんがいる、猫などがいる場合は、逆に仕事に集中できない場合もあります。
十分な執務スペース、環境が確保できない場合は、生産性が落ちる可能性もあります。
また、業務態度などが見えない分、成果のみで評価することになります。
評価基準はしっかりと作成すべきですが、何となくの評価にはなりにくいので、成果主義に近づいていきます。
そして、働き方が柔軟になるので、子育て世代、介護世代でも、時間や場所に縛られることなく働くことができます。
諸事情により働きにくかった優秀な人材を採用する選択肢も広がります。
その他
電話の転送や仕事用携帯の準備なども必要になるでしょう。
直ぐに相談できなかったり、雑談できなかったり、場所を共有できないデメリットもあります。
その場合は、監視という意味ではなく、繋がりを持つという点で、zoomを繋いでおいても良いかもしれません。
まとめ

【準備するものリスト】
- ノートパソコン
- リモートツール(チームビューアなど)
- スマートプラグ
- テレビ電話ツール(zoomなど)
- チャットツール(チャットワークなど)
- ファイル共有ツール(ドロップボックスなど)
- 守秘義務契約書・宣誓書
- 業務の仕分けと分担の整理
- 作業割当(在宅と事務所作業の整理)
- 評価基準の作成
- 電話転送など
準備は大変ですが、一度整理しておけば今後も活用することができます。
リモートワーク導入のメリット
- 外出困難な場合でも業務を継続できる
- 業務の見直し、整理ができる
- 業務効率を上げるチャンス
- 出勤する時間と負担がなくなる
- 採用の幅が広がる など
- リモートワークをしている仲間とスムーズに仕事ができる
メリットが沢山ありますので、最初から完璧は無理ですが、この機会にできる範囲でやっていきましょう。
完璧にはできていませんが、部分的にでも導入してみて良かったです。
少しずつでも部分的にでもまず取り組んでみることが大事だと思います。